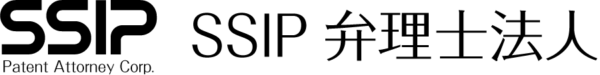クレームセットの最適化
全ての国(地域)に共通するグローバル明細書の工夫として、拒絶されにくい従属請求項の作成が挙げられます。
では、拒絶されにくい従属請求項とはどのようなものでしょうか。
SSIPは、長年の中間処理業務の経験から、“発明の構成同士の関係を特定した内的付加”の従属請求項が審査段階において拒絶されにくいと考えます。
発明の構成同士の関係を特定した内的付加
発明の構成同士の関係を特定した内的付加とは、独立請求項で既に特定されている複数の構成の関係を従属請求項で特定することを意味します。
例えば、構成A及びBを特定した独立請求項(A+B)に対して、審査官が、手持ちの先行技術文献として、構成Aを開示した引例1と、構成Bを開示した引例2を保有しているケースを考えます。
この場合、独立請求項(A+B)については、論理付けさえできれば引例1と引例2との組み合わせにより、進歩性欠如により拒絶されてしまいます。これは、拒絶理由通知書で非常によく目にする一般的なケースです。
ここで、大事なポイントは、審査官は、構成Aと構成Bの両方を開示した先行技術文献を発見できていないことです。
(もしそのような完全な先行技術文献を見つけていれば、この文献を用いて、A+Bの請求項を新規性欠如により拒絶したはずです。そうではなく、引例1と引例2との組み合わせに基づく進歩性欠如の拒絶理由を指摘しているということは、審査官は、構成Aと構成Bの両方を開示した先行技術文献を発見できなかったということです。)
このため、構成Aと構成Bの相互の関係「a1 & b1」を特定した従属請求項については、審査官の手持ちの引例1および引例2の何れにも開示も示唆もされていない具体的な構成が特定されているため、下図に示すように、審査官としてはお手上げ状態になります。
審査官の手持ちの引例を組み合わせても「a1&b1」の構成が得られない

まとめ
独立請求項の複数の構成を別々に開示する引例が発見されたとしても、これらの構成の相互関係を限定した内的付加の従属項を作っておけば特許性ありとの判断結果を期待できます。
SSIPのグローバル明細書では、内的付加の限定事項を含む従属項を可能な限り多くクレームセットに盛り込んでいます。このため、初回の審査結果(PCT出願なら国際調査報告)で許可クレームを作って、その後の審査を有利に進めることができます。
\ グローバル明細書で海外出願の最高のスタートを!/