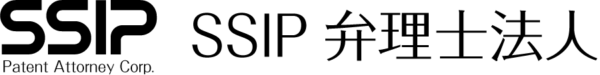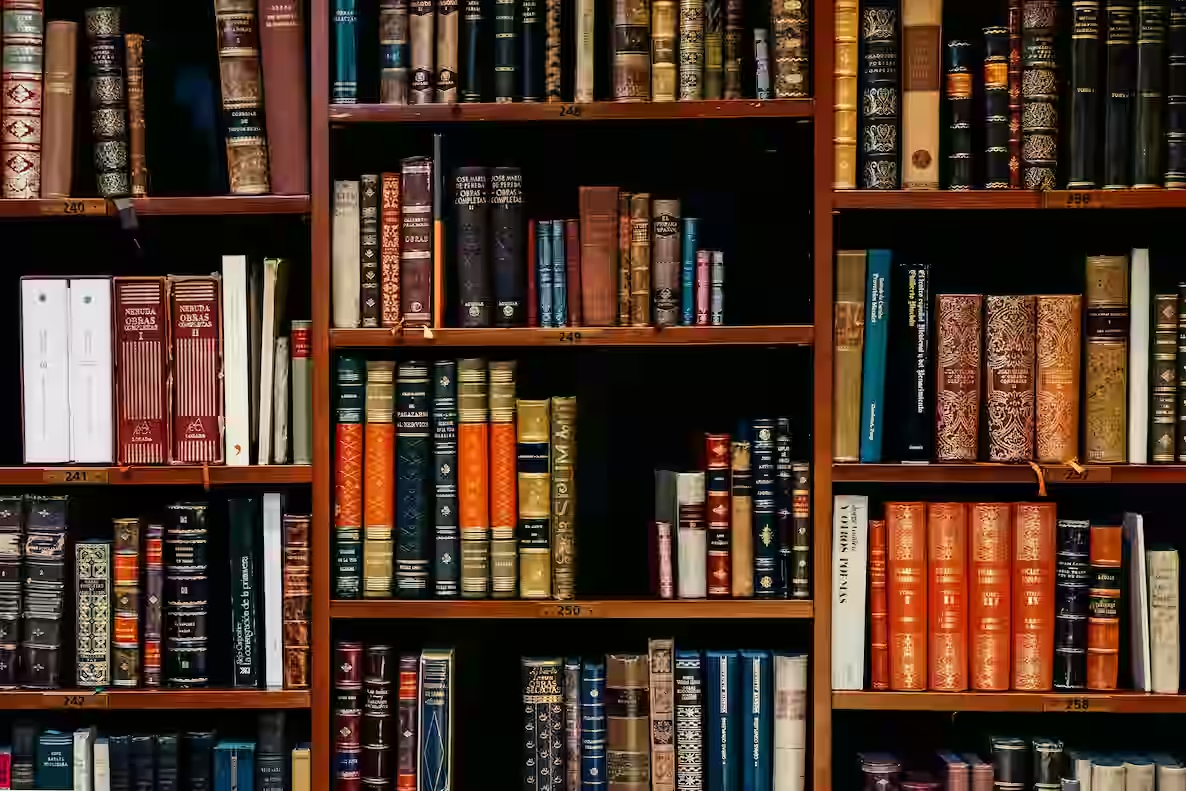海外に特許出願する2つの方法と費用の違い
海外で特許を取得する方法として、以下のとおり、2つのルートがあります。
海外への特許出願ルート
- 直接各国に出願する方法(パリルート)
- 国際出願経由で各国(約150国から選択可能)に移行する方法(PCTルート)
どちらのルートにおいても、基礎となる日本出願用の費用に加えて、外国出願に関する費用が別途必要になります。
これら2つの方法は、出願するまでのプロセスも異なれば、費用項目や費用の発生タイミングも異なります。
一概に、どちらの方法が安い・高いと言うことは難しいですが、特許を取りたい国や地域を考慮して、どちらの方法が経済的であるかを検討する必要があります。
最終的にどちらの方法で出願すべきかは、費用以外の違いも考慮して決定すべきですが、ここでは、それぞれの方法の費用面での違いについてみていきましょう。
パリルート
パリルートでは、通常、日本に第1国出願(通常の国内出願)を行った後、優先期間内(1年以内)にパリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して、第2国(海外特許を取りたい国)に出願をします。
第1国出願では、日本語の出願書類を作成済みですが、第2国出願は対象国の言語で作成した出願書類が必要になります。そこで、優先期間(1年)を利用して、日本語の出願書類を各国の言語に翻訳します。
特許出願書類の翻訳は、一般文書の翻訳とは異なり、特許の専門知識が必要になるため、通常は特許事務所や特許専門の翻訳者に依頼することになります。
パリルートによる外国出願の流れをまとめると以下のとおりです。
パリルートによる外国出願の流れ
通常の国内出願と同様に、日本語の出願書類を作成して、日本の特許庁に出願します。
出願対象国を決定し、その国に応じた準備を行います。
第1国出願は日本語で行っているので、出願対象国の言語への翻訳文が必要になります。
第1国出願から1年以内に対象国に出願する必要があります。
対象国の特許事務所(現地代理人)を通じて、対象国の特許庁に出願します。
続けて、パリルートで外国に出願する場合の費用について、説明します。
まず、日本語で作成された第1国出願の翻訳料が必要となります。
また、第2国への実際の出願手続きは基本的に現地代理人(その国の弁護士又は弁理士)を介さなければなりませんので、現地代理人の手数料(現地代理人費用)が必要になります。
また、日本と同様に、その国の特許庁に対して法定の出願手数料も支払わなければなりません。
さらに、日本国内の特許事務所は、外国出願を希望する出願人様と、実際に外国で手続きを行う現地代理人との間の仲介をすることになりますので、所定の手数料(国内代理人費用)がかかります。
以上をまとめると、パリルートの場合、以下の費用が発生します。
パリルートの場合の費用
- 第1国出願の費用
- 日本語で作成された第1国出願の出願書類の第2国の言語への翻訳料
- 第2国出願の手続きを担当する現地代理人(その国の弁護士又は弁理士)に支払う手数料
- 第2国の特許庁に対して支払う出願手数料
- お客様に代わって現地代理人をコントロールする国内の特許事務所に対して支払う手数料
言語の種類にもよりますが、第1国出願から1年以内(優先期間内)に、翻訳料、現地代理人費用がまとめて必要となりますので、後述するPCTルートに比べて出願時の初期コストが高くなる傾向があります。
1か国あたりの外国出願に要する費用は、現地代理人費用や出願手数料は各国ごとにバラバラなのであくまで目安ですが、50万~120万円程度(国内代理人費用を入れると80万~150万程度)になるでしょう。
金額の幅が大きいのは、出願書類の分量によって翻訳料が大きく変わること、そもそも英語の翻訳文を複数の国で流用できる場合には翻訳自体が不要になるといった個別の事情に左右されるためです。
このように、パリルートによる外国出願では、第1国出願から1年以内という短い期間で、大きな金額の支払いが発生します。
PCTルート
通常、外国で特許を取得したい場合は、国ごとに個別に特許出願の手続きをしなければなりません。
先ほど説明したパリルートの場合でも、第1国の出願日から1年以内に、対象国に個別の特許出願の手続きを行う必要がありました。
しかし、PCTルートなら、まずは日本語で国際出願(PCT出願)をすることで、各国に対して、一括で特許出願をする権利を確保することができます。少し難しい言い方で表現すれば、PCTルートにおいて、国際出願は、単一の言語および形式の出願をするだけで、 複数国での国内出願としての効果が生じます。
ただし、実際に各国で特許を取るためには、国際出願から所定期間(原則、30ヵ月以内)に各国特許庁に対して国内移行という手続きを個別に行う必要があります。
このように、PCTルートの場合、国際出願から30ヵ月という猶予期間があるので、時間をかけてじっくり、対象国を検討したり、翻訳を準備することができます。
費用面についても、最初は日本語で国際出願(PCT出願)だけしておけばいいので、この段階では高額な翻訳手数料や現地代理人費用は不要です。このため、初期コストを大幅に抑えることができます。
このように、PCTルートなら、外国出願の判断も費用も先送りに出来ることが非常に便利です。
PCTルートでの外国出願の流れをまとめると以下のとおりです。
PCTルートでの外国出願の流れ
日本語で出願書類を作成して、日本の特許庁に国際出願します。
国際調査機関(日本特許庁)が、発明について先行技術を調査し、特許取得の可能性についての見解を示します。
権利を取りたい対象国(移行国)を決定し、その国に応じた準備を行います。国際出願は日本語で行っているので、移行国の言語への翻訳文が必要になります。
国際出願から所定期間(原則、30ヵ月以内)に対象国の特許庁に対して国内移行手続きを行う必要があります。この手続きは、移行国の特許事務所(現地代理人)を通じて行います。
なお、PCTルートで外国に出願する場合の費用についても簡単に説明します。
まず、日本語で作成された国際出願の翻訳料が必要となります。
また、各国特許庁に対する移行手続きは基本的に現地代理人(その国の弁護士又は弁理士)を介さなければなりませんので、現地代理人の手数料(現地代理人費用)が必要になります。
さらに、日本と同様に、その国の特許庁に対して法定の手数料も支払わなければなりません。
さらに、日本国内の特許事務所は、外国出願を希望する出願人様と、実際に外国で手続きを行う現地代理人との間の仲介をすることになりますので、所定の手数料(国内代理人費用)がかかります。
PCTルートの場合の費用
- 国際出願の費用(国際調査・国際予備審査手数料を含む)
- 日本語で作成された第1国出願の出願書類の移行国の言語への翻訳料
- 国内移行手続きを担当する現地代理人(その国の弁護士又は弁理士)に支払う手数料
- 移行国の特許庁に対して支払う国内移行手数料
- お客様に代わって現地代理人をコントロールする国内の特許事務所に対して支払う手数料
なお、国際出願手数料(30枚まで)は、230,500円(オンラインは-52,000円)
調査手数料は国内の特許庁が行う場合は143,000円(欧州特許庁が行う場合は300,000円)
国内代理人の手数料は、難易度にもよりますが、1件あたり25~40万円
という金額なので、PCTルートでは、国際出願に、55~70万円程度の費用を要します。
もちろん、PCTルートでも、国内移行手続きを行う段階で、パリルートの場合と同様な項目(翻訳費用や現地代理人費用等)が発生するのですが、PCTルートでは、移行国が多いほど、トータル費用を抑えることができます。
また、各国移行手続きのタイミングは、国際出願から30ヵ月以内であり、国際出願を行った後、大きな費用が発生するまでに十分な時間的猶予があります。
この期間に、海外事業の状況変化に応じて移行国を適切に選択すれば、無駄な費用の発生を防げます。
また、PCTルートの特徴である国際調査報告書を活用すれば、国際出願時に想定していなかった強力な先行技術が発見された場合に、各国移行自体を取りやめることも可能です。
まとめ
PCTルートは、猶予期間が長く、国際調査の結果を利用した外国出願の要否決定が可能である点で、パリルートにはないメリットがあります。
その一方で、移行国数が少ないとパリ条約ルートより権利化までのトータル費用が高額になってしまう場合があります(目安としては、3-4カ国以上の国で権利化を希望する場合にはPCTルートを選択し、それ以下の移行国数であればパリ条約ルートを選択するというのがコスト的におすすめです)。
他にも考慮すべき事項がありますので、どちらのルートが適切か迷ったら、当事務所までお問い合わせください。
\無料相談はこちら/
また、費用対効果を考えれば、ただ海外で特許を取ればいいということではなく、各国で強い権利を取得する必要があります。そのためには、日本語明細書を作成する段階から、各国の特許実務の違いを考慮して内容面で工夫する必要があります。
SSIPでは、諸外国の特許実務の違いを考慮して内容を工夫した日本語明細書(「グローバル明細書」)を作成します。日本語明細書を作成する段階で行うべき工夫を漏れなく実施することで、各国で最大範囲の権利を取得することができます。